お問合わせ
CONTACT
MEDIA
CATEGORY
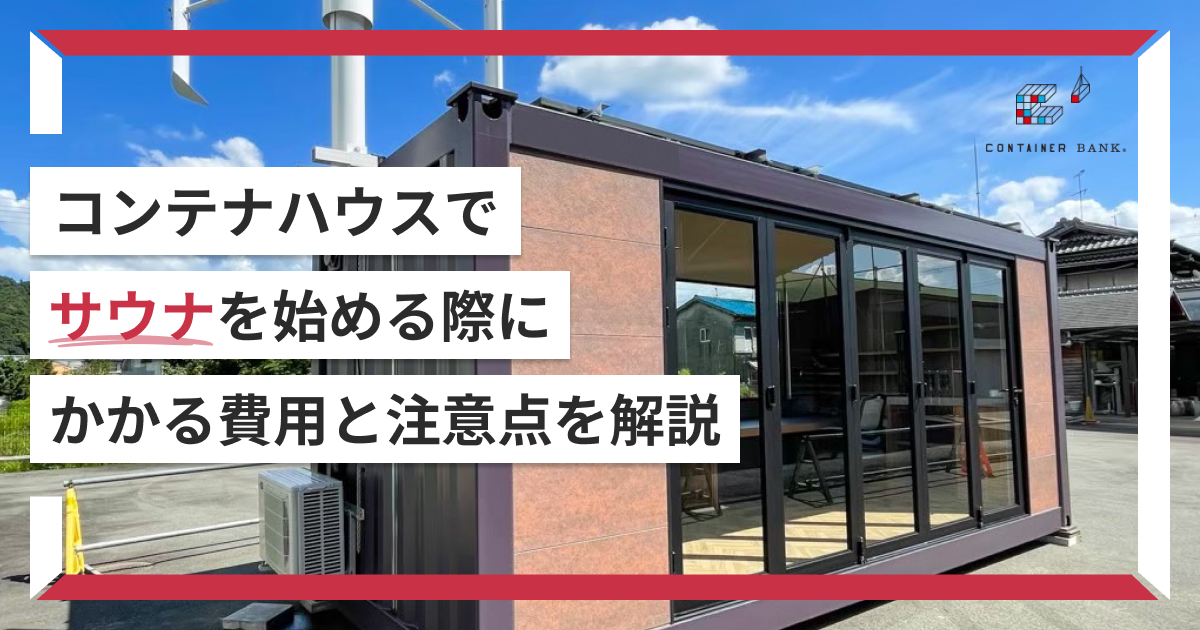
サウナを設置したいと考えている方の中には、コンテナハウスの活用を考えている方もいるでしょう。
コンテナハウスでサウナを始める際には、通常のサウナを設置する以上にいくつか注意すべき点があります。当記事ではサウナを始める際の注意点を解説します。サウナ設置にかかる費用も合わせて解説するので、参考にしてください。

サウナを建てる場合にかかる費用には、コンテナハウス本体や輸送費をはじめ、サウナに必要なサウナ室や照明などの内装や設備費などがあります。
【コンテナハウスの費用目安】
| 経費 | 詳細 | 金額 |
| 本体代 | 20フィート | 中古:20万円前後
新品:120万円前後 |
| 40フィート | 中古:30万円前後
新品:200万円前後 |
|
| 輸送費 | 20フィート | 4万円~18万円前後 |
| 40フィート | 7万円~30万円前後 | |
| 工事費 | 基礎工事 | 1フィート当たり1万円
※傾斜地と平坦地によって異なる場合がある |
| 電気工事 | 10万円~15万円程度
※電力会社や電気工事業者によって異なる |
|
| 給排水設備工事 | 200万円~300万円程度
※水回りをすべて設置した場合 |
|
| 改装費 | 外装(塗装、断熱処理、防錆対策など) | 10万円~数十万円程度
※デザインや材質によって異なる |
| 内装(コンテナ内のデザイン) | 坪単価50万円~100万円程度
※デザインや材質によって異なる |
|
| 設備費 | ドア・サッシ・エアコンなど | 100万円~200万円程度
※設備の数や材質によって異なる |
コンテナハウスでサウナを始める場合、大切なのは断熱対策や換気対策です。コンテナハウスは熱が伝わりやすく、結露や湿気にともない錆が発生しやすい材質であるためです。外装工事の際は、費用は高くなりますが内断熱と外断熱を組み合わせることで断熱性をより高めることができます。
また、コンテナハウスを長期的に活用する際はメンテナンスが必要です。防サビ対策やシロアリ対策であれば、3年~5年に一度メンテナンスが求められます。
コンテナハウスにかかる維持費が知りたい方は「コンテナハウスの維持費は年間どれくらい?維持費の種類や抑える方法も解説」を参考にしてください。
なお、コンテナハウスでサウナを始める場合は、コンテナハウスにかかる費用に加えてサウナ機器や設備にかかわる費用も必要になります。初期費用と維持費をあらかじめ計算した上で、予算計画を立てるようにしましょう。
コンテナハウスで使うサウナのストーブは、薪ストーブより電気式のストーブや遠赤外線ヒーターの方が、火災のリスク管理がしやすい傾向にあります。サウナ機器には多様な種類があり、セット内容も販売元によって異なるため環境や目的に応じて慎重に選びましょう。
一方で、薪ストーブには電気式では味わえない格別な魅力があります。パチパチと薪がはぜる音、本物の炎の揺らめき、そしてじんわりと体を芯から温める柔らかな熱波は、五感を満たす深いリラクゼーションを生み出します。
弊社では、こうした本格的なサウナ体験を安全に楽しんでいただくため、断熱や換気に最大限配慮したオリジナルの「薪ストーブ付きコンテナサウナ」を開発・ご提案しております。コンテナサウナに少しでもご興味があれば、是非お問い合わせください。
【サウナ機器一式の費用内訳】
| サウナ(構造) | 費用目安 | 特徴 |
| テントサウナ | 5万円~30万円 | 簡易的で持ち運び可能。コンテナハウス内での使用は換気・火災リスク管理が必須。 |
| バレルサウナ(屋外設置) | 100万円~200万円 | 樽型でデザイン性が高い。主に屋外設置用。コンテナハウス横に併設する形が多い。 |
| サウナ(熱源) | 費用目安 | 特徴 |
| 遠赤外線サウナ(据え置き型) | 30万円~50万円 | 比較的コンパクトで省スペース。電気工事が比較的簡易な場合が多い。ロウリュはできない。 |
| 電気式ストーブ型サウナ(据え置き型 | 40万円~180万円 | 樽型でデザイン性が高い。主に屋外設置用。コンテナハウス横に併設する形が多い。 |
サウナのセット内容にサウナストーンやタイマー、温度計などが入っていない場合は、自身で購入する必要があります。備品をすべて揃えると数万~数十万程度かかるため、サウナ機器をセットで購入する際は、セット内容をあらかじめ確認しておきましょう。
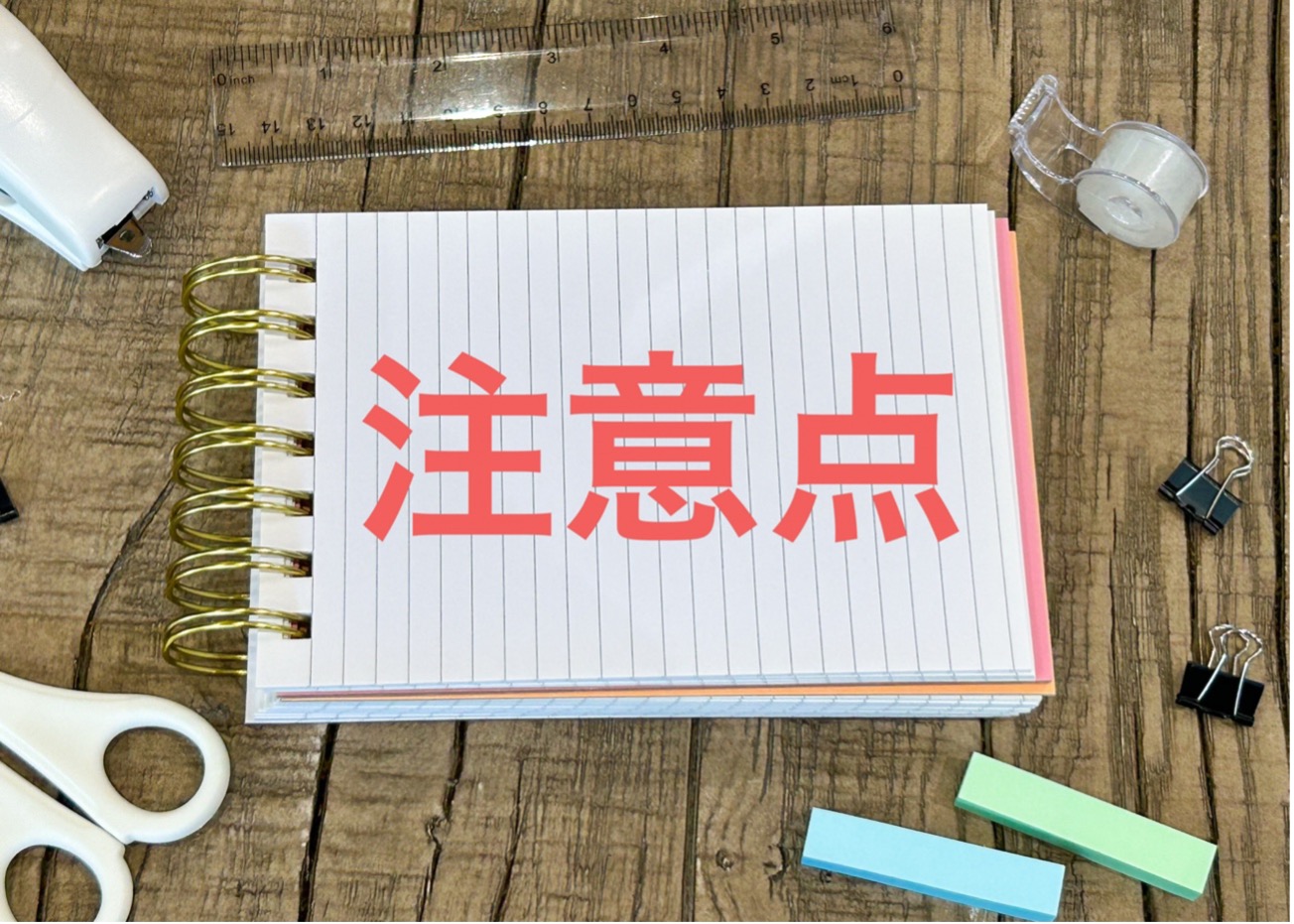
コンテナハウスでサウナを始める際は、断熱対策や設備点検など、定期的なメンテナンスが必要になります。また、安全性や健康被害を起こさないために、専門的な知識が必要になるため、専門業者の意見を取り入れながらデザイン設計を進めましょう。
【コンテナハウスでサウナを始めるときの注意点】
上記で挙げた注意点以外にも、建築基準法や消防法などの法律に関する知識も求められます。立地の制限や防災および避難などへの配慮が必要になるため、コンテナハウスの設置を検討している方は、コンテナハウスにかかわる法規制を調査しておくことが望ましいです。
コンテナハウスでサウナを始める際は、木造建築でサウナを始めるよりも丁寧な断熱対策や防水対策が求められます。コンテナハウスは鉄でできており、結露しやすく湿気などでサビやすい性質を持っているためです。
断熱対策の場合、断熱材の種類や断熱方法によって効果や費用が異なります。内断熱と外断熱を組み合わせることで断熱性能が高くなりますが、費用も高くなる傾向があります。
【断熱方法による費用の目安】
| 断熱方法 | 詳細 | 金額 |
| 発泡ポリウレタンフォームによる吹付断熱 | ・材料費が高価だが、断熱性能・気密性に優れている
・施工の難易度は高め |
1万円~2万円程度 |
| 外断熱 | ・材料費が高価だが、断熱性が高く、結露の発生を防げる
・施工の難易度は高め |
1.5万円~3万円程度 |
| 内断熱 | ・材料費は安価な傾向
・施工の難易度は低め |
5千円~1万円程度 |
コストを抑えたい場合でもある程度の安全性は確保する必要があるため、余裕をもった予算計画を立てることが望ましいです。コンテナハウスは「夏に暑く冬に寒くなる」ため、丁寧な断熱対策を行い、ヒートショックやその他の健康被害を防ぐようにしましょう。
防水対策には、壁の内側に防湿シートを貼り付け、屋根や壁の外側に防水塗料などを塗布する方法があります。適切な換気設備も整備し、カビやコンテナの腐食を予防することが求められます。
サウナを設置する際は、消防設備の設置と点検も必要です。各市町村でサウナに関する火災予防条例が定められており、東京消防庁のサウナ設備に関する資料には、消防用設備に関して基準が設けられています。
【東京消防庁のサウナ設備に関する資料から一部引用】
(オ) 対流型サウナ設備に設ける消防用設備等は、法令の基準によるほか、次によること。◆
a 対流型サウナ室が次のいずれかに該当する場合は、消火装置を設けること。
⒜ 高さ31mを超える階、地下街、地階、無窓階、鉄道高架下の部分に設置する場合
⒝ 一の対流型サウナ室の床面積が、20㎡を超える場合引用元:東京消防庁:第9 サウナ設備
なお、火災予防条例の内容は各市町村によって異なるため、サウナを設置する市町村の火災予防条例を確認する必要があります。コンテナハウスでサウナを設置する際は、防災や避難に配慮することも忘れないようにしましょう。
コンテナハウスにサウナを設置した後は、初回使用時に2~3度空焚きを行いましょう。サウナの内装に木材を使用した際、木材を加熱すると、リグニンやヘミセルロースなどの成分が熱分解を起こし、ホルムアルデヒドを含む揮発性有機化合物が生成されることがあります。
ホルムアルデヒドは人体に有害な化合物です。目や鼻への刺激、頭痛やめまいなどのシックハウス症候群の症状やアレルギー症状を引き起こす可能性もあります。
初回使用時は、換気を徹底した状態でサウナストーブをつけて室内を十分に温め、数時間空焚きを行いましょう。数回繰り返すことで、初めて使用する建材から出てくるホルムアルデヒドを排出できます。
他の対策として「コンテナハウスに使う建材を、ホルムアルデヒドの放散リスクが極めて低い無垢材にする」、「ホルムアルデヒドを含まない接着剤や塗料を選ぶ」なども効果的です。
水風呂を設置する場合は、コンテナハウスの床が水風呂を入れた時の総重量に耐えられるかも確認しておきましょう。水の重さに加えて、人と浴槽の重さを考慮する必要があります。
【コンテナハウスの床の耐荷重目安(標準)】
| コンテナの大きさ | 最大積載量 | 1㎡あたりの耐荷重 |
| 20フィート | 約15,000 kg | 約1,000 kg/㎡ |
| 40フィート | 約25,000 kg | 約1,000 kg/㎡ |
家庭用浴槽の水を満水に入れたときの総重量を、900キログラム程度とします。コンテナハウスの耐荷重は、20フィートコンテナなら1平方メートルあたり1,000キロ=1トンが目安となります。
ただし、サイズやコンテナの種類、販売元、コンテナハウスと海上輸送コンテナの積載量は異なり、特別に床荷重を求める場合には床下補強が必要になります。コンテナハウスのサウナに水風呂を設置する際は、コンテナハウスの販売元に床の耐荷重や総積載量の確認をしておきましょう。
サウナを建てる場合にかかる費用には、コンテナハウス本体や輸送費をはじめ、改装費や設備費などがあります。他にも、メンテナンス費用やサウナ機器にかかる費用も準備しておく必要があります。
コンテナハウスでサウナを始める際は、断熱対策やホルムアルデヒド対策など専門的な知識が必要です。建築基準法や各市町村で異なる火災予防条例などにもかかわるため、事前に専門業者に相談しながら、安全性や健康被害に配慮した設計を検討しましょう。